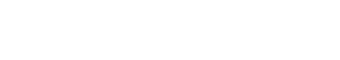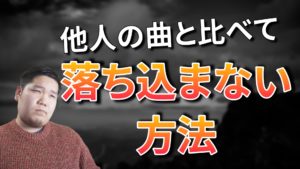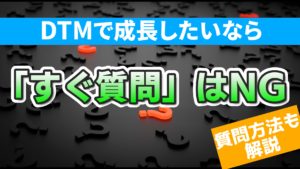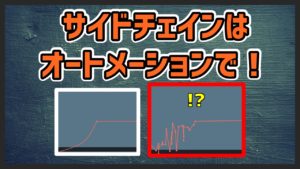ドラムは曲のクオリティを左右する重要なパートです。
そんなドラムの音はミックスによって作られるんですが、この作業がかなり難しいんですよね。
ドラムには何本ものマイクを立てて録音するんですが、本格的なドラムのミックスをするときには、それぞれのマイクで録った音に別々の処理をしていくのが普通。
ちなみに、ドラムのミックスで処理するトラックは以下のようになっています。
- オーバーヘッドマイク
- バスドラム
- スネア
- ハイハット
- タム
- ルームマイク
- バストラック
一言にドラムといっても、これだけのトラックで作られているので、そりゃミックスも難しくなりますよね。
今回は、このそれぞれのトラックを処理するときのポイントをざっくり解説していきましょう。
オーバーヘッドマイクを土台にしていく

- 位相を合わせる
- ローカット
- サチュレーション/ディストーションでシンバルのキラキラ感をコントロール
- 速めのコンプでがっつり潰す
マイクの場所的にドラムセット全体の音をバランスよく収録できているので、ドラムのミックスで一番重要なマイクはオーバーヘッドマイクです。
オーバーヘッドマイクを土台として、それにキャラクターや響きを付け足すイメージでミックスをするとやりやすいでしょう。
ドラムセットから少し離れた場所に設置してあることが多いので、まずは位相を個別のマイクに合わせることからスタートします。
次いで、シンバルはオーバーヘッドマイクにしか収録されていないことが多いので、ローカットをして相対的にハイを強調させていきましょう。
それでもシンバルのキラキラ感が足りない場合は、EQでハイを強調するよりも、サチュレーションやディストーションを薄っすらかけてあげるほうが上手く場合が多いです。
また、オーバーヘッドマイクはバスドラやスネア、タムなどがが入ったり抜けたりして音量差があるので、速めのコンプでがっつり潰してあげるといい感じになります。
バスドラムで曲のノリをコントロール

- ベースと棲み分ける
- ギターやシンセは必ずローをカット
- ハイで存在感を調節
バスドラムは曲のノリをコントロールする重要なパートです。
同じ曲でもバスドラムの音量が違うだけでノリが強調されたり、逆に控えめにすることもできます。
いろいろな曲を聴いてみて、バスドラの存在感を確かめてみると自分のミックスに生かしやすいでしょう。
バスドラムのミックスで重要なのが、やはりベースとの棲み分けです。
その際に、ギターやシンセも低音が出ていると棲み分けが更に面倒になるので、まずは低音が必要ないパートはローカットしておきましょう。
ベースとの棲み分け方法は大きく分けて以下の3通り。
- ベースが上の帯域、バスドラが下の帯域を担当する
- バスドラが上の帯域、ベースが下の帯域を担当する
- 帯域を共存させ、音量で棲み分けさせる(サイドチェインコンプ)
この3つを意識して、耳で聴きながら処理しましょう。
DTMでよく使われるようなニアフィールドモニターだと低音が出ないので、低音の処理はヘッドホンでやるとやりやすいです。
よく、DTM関連の書籍やネット記事などで「〇〇Hzをカットしてベースの帯域を空けて~」など、Hzを指定するものがありますがあんまり当てになりません。
素材によって処理の方法は臨機応変に変わっていきますし、目指しているミックスによっても棲み分け方は変わります。
また、バスドラムの存在感はアタックの音にも左右されるので、ローだけでなくハイも気にしながらミックスをしていきましょう。
スネアはリリースでノリを作る

- 位相を合わせる
- オーバーヘッドマイクに芯を足すイメージ
- ボーカルと棲み分ける
- リリースでノリを調整(ルーム/オーバーヘッドとの兼ね合い)
スネアはトップとボトムで別々に録る場合、位相が逆になるので、まずはどちらかの位相を反転させて、位相合わせ作業をしていきましょう。(オーバーヘッドマイクとの位相の兼ね合いもあるので、通常はボトムの位相を反転させるほうが無難です)
その後のスネアのミックスは、基本的にオーバーヘッドマイクに芯を足すイメージでやっていきます。
ミドルの帯域はボーカルがメインになってくるので、音の被りが気になる場合は、ミドルをカットすることも重要です。
また、スネアのリリースでノリが全く変わってくるので、ゲートやエキスパンダー、必要ならオートメーションも駆使しつつリリースをコントロールしていきます。
トップとボトムで処理を変えることもよくあるので、色々と試してみましょう。
よくあるのは、ボトム側のスナッピーサウンドをゲートで短く切って余韻を少なくする処理など。
これだけでスネアが前に出てきます。
ハイハットは出し過ぎない

- オーバーヘッドマイクで足りるかを考える
- 単品マイクを使う場合は、前に出す感じで
ミックス初心者の大半はハイハットが大きすぎます。
ハイハットのミックスで考えるべきは、わざわざ単品マイクを使う必要があるのかということ。
ハイハットはオーバーヘッドマイクにかなり入ってきていますし、スネアのマイクにも録音されます。
それにわざわざ単品マイクからの音を使うことで、バランスが取れなくなってしまうというのはミックス初心者ではありがちな失敗です。
僕が単品マイクを使うときは大抵、ハイハットを前に配置したい場合ですね。
ただ、その場合でも位相をしっかり合わせないと使い物にならないことが多々あります。
どちらかというとミックスよりもマイキングが難しいですね。
逆に言えばマイキングさえしっかりしてあるなら、フェーダーのコントロールとローカットくらいで十分でしょう。
タムは定位が大事

- PANをきっちり振る
- フロアタムのリリースは長過ぎないように
- バスでまとめると音量管理が楽
バスドラム・スネア・ハイハットの音はカッコイイのに、タムが入るフィルであららとならないように気をつけたいところ。
タムでのポイントはPANをきちんと振って、フィルのときに流れるように聴かせることでしょう。
PANの振り幅はわりと自由ですが、狭めだとキット感が強調され、広めだと独立感が強調されるという特徴があるので心に留めておいてください。
あまり左右に広げすぎるとLRのバランスが悪くなるので、筆者の場合は最大でも60%~80%の間で収めるようにしています。
フィルのフレーズを聴いたときに、太鼓ごとに音量がバラバラだと聴きにくいので、コンプやオートメーションで音量のバランスを取るのも重要です。
ローカットについては、ハイタム/ロータムはわりとガッツリ、フロアタムはバスドラムとの兼ね合いでポイントを探すといった感じですね。
また、フロアタムはリリースが長すぎるとキックやベースと被るので、ゲートなどで調整していきます。
ルームマイクでキャラクターを付ける

- 位相を合わせる
- 響きでキャラクターをコントロールする
ルームマイクはアンビエンスマイクとも呼ばれる、部屋鳴りを録るマイクのこと。
ドラムキットからある程度距離を空けて設置されるので、まずは位相を合わせていきましょう。
このルームマイクは使い道がいろいろあるのですが、基本的にはドラムのキャラクター付けに使われることが多いですね。
具体的には、ルームマイクの音量を上げていくとライブ感が強調され、逆に下げていくとデッド感が強調されていきます。
ロックなどでは他の音にかき消されてしまうので、コンプでがっつり潰してコンプのリリースで響き感を調整してみてください。
バストラックでまとまり感を作る

- バスコンプでまとめる
- キックは独立させることも多い
ここまでやってきても、なんだかドラムキットがバラバラな感じがすることも多いです。
そんなときにはバストラック(ドラムキットをまとめたトラック)に対してバスコンプと呼ばれるタイプのコンプを書けてまとまり感を出していきましょう。
バスコンプをかけることで、同じ量/質感のコンプレッションがかかるので、トラックに一体感が出てきます。
また、最近のミックスはバスドラの音を強調する場合が多いですが、バスコンプだと大きすぎるバスドラだけに反応してしまうこともありますよね。
そんなときにはバスドラムだけバスコンプを外すというのもいいんですが、HPFがついたコンプなら低音だけをコンプから逃がすことができるのでやってみてください。
ちなみにバスコンプを持っていないという人もいますよね。
バスコンプはミックスでよく使うプラグインなので1つくらいは持っておいて損はありません。
有名なものだとWavesの最高傑作とも呼ばれる、「Waves SSL 4000 Collection」にバンドルされてるSSL G-Masterなどがプロアマ問わず人気です。
Wavesはセールで10分の1くらいの価格になっていることも多くなりました。
Amazonやサウンドハウスでは、セール期間外でもセール価格で売っていることも多いので、すぐに必要な人はぜひチェックしてみてくださいね。
もちろん、それ以外にもさまざまなバスコンプがあるので、色々と調べてみましょう。
筆者はAbleton Liveユーザーなのですが、Liveに付属している「Drum Buss」というバスコンプをよく使っています。
これを使うだけで音がものすごくまとまりますし、積極的に音作りもできるので、Ableton Liveユーザーでまだ使ったことがないという人はぜひ試してみてください。
おわりに
最後にまとめると、
- オーバーヘッドマイクはミックスの土台に
- バスドラムで曲のノリをコントロール
- スネアはリリースでノリを作る
- ハイハットは出し過ぎない
- タムは定位が大事
- ルームマイクでキャラクターを付ける
- バストコンプでまとまり感を作る
となります。
ドラムのミックスはやり方が人によって違いますが、まずはこの基本的な技術をマスターしましょう。
また、筆者は音楽関連の講座動画をYouTubeでたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録お願いします!
筆者のツイッターはこちら!