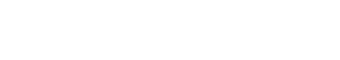ゲームや動画のBGM、アーティストが演奏する曲など、音楽制作を依頼したいけれど予算がなくてできないということもありますよね。
そういうときに、安く依頼できないかクリエイターに相談しても、内容に納得できなければ当然依頼は断られてしまいます。
筆者は作編曲家でもあるんですが、依頼を請ける立場として、いくらしつこく粘られても無理なものは無理と断っています。
ですが、実は音楽制作の価格交渉にはちょっとしたコツがあるんです。
今回は筆者がクリエイターの視点から、価格交渉をするときのコツをいくつか紹介しましょう。
イメージはできるだけ具体的に

安く依頼したいときには、できるだけ完成イメージを具体的に伝えましょう。
よく「安い仕事だから資料も適当、ざっくりで作ってもらおう」と考えている方がいらっしゃいますが、実はそういう場合の方が手間が掛かってしまうんです。
考えてみれば分かりますが「1000円あげるから僕好みのご飯作って」というのと「1000円でオムライス作って」だったら後者のほうが絶対楽ですよね。
それと同じで、音楽もできるだけ完成形を提示してあげたほうが作りやすいんです。
なので、安く依頼したいときには資料を作り込んできっちりと方向性を伝えるなど、クリエイターの考える時間を減らせる工夫をしましょう。
作家の作業量を減らす
音楽制作は面倒な作業がかなり多いので、それらが積み重なって作業時間が伸び、料金の増加につながってしまいます。
クリエイター側としても面倒な作業はできるだけやりたくないというのが本音。
なので、クライアント側でできる作業はやらなくていいと提案すればクリエイター側も料金交渉に応じてくれることも多いです。
例えば、先程のしっかりとした資料を作るのもそうですし、ボーカルのピッチ・リズム補正を引き受けてくれるといったことでももちろんOK。
できるだけリテイクの回数を減らすというのもいいでしょう。
複数の曲をまとめて依頼する

いわゆる「グロス発注」などと言われる依頼方法。
例えば1曲5万円が正規料金だけれど、10曲まとめてなら40万円でOKですよ、といったことがよくあります。
クリエイターは仕事が不定期で収入が不安定になりがちなので、まとまった仕事があるとありがたいんです。
また「一度にまとめて」ではなくても、「今後1年間で月1曲ずつ」といった定期的な製作依頼をすると1曲あたりの値段を下げられる場合もあります。
金銭以外のメリットを提示する
これもよくありますね。
多くのクリエイターは依頼の金額だけで受ける仕事を決めているわけではないので、楽しそうな仕事やメリットが多い仕事なら安くても請けます。
逆に言えば高い仕事でも、つまらなそうなら請けないという人も多い業界です。
クリエイター側にメリットが大きい仕事は、安くても引き受けてくれるかもしれません。
とはいえ、そのクリエイターにとって何がメリットなのかをしっかりと考えなければあんまり意味がありませんが……
作家が持つ権利を大きくする

契約面で、作家が持つ権利を大きくしてあげるというのも価格交渉ではよくあります。
クライアント側が独占使用権だけ持って他の権利はクリエイター側などが多いですかね。
クリエイター側の権利が小さい、「権利は全部買い取りです」という契約だと将来的に何の資産にもならないので、金額は高くなってしまいます。
その作家にとって新しいフィールドの仕事を依頼する
今まで歌モノを作っていたクリエイターに劇伴やBGMの仕事を依頼するなど、そのクリエイターにとって新しいフィールドの仕事は安く請けてくれる可能性が高いです。
クリエイター側にとっても初めての分野ということで、、相場感もあまり無く、上手く出来るかわからないので価格を上げにくいというのが本音。
新しい仕事で上手く行けば、将来的に仕事の幅を広げられるというメリットもあるので、はじめてのフィールドの仕事は安く受けるというのはよくあります。
おわりに
高くて依頼できないようなクリエイターでも、実は内容によっては安く依頼できることもよくあります。
ぜひ予算がないと諦めないで、条件を提示をするなどして交渉してみてはいかがでしょうか。
もちろん今回のコツはあくまで例なので、これ通り交渉しても上手くいかない場合はありますが、試しに連絡して聞いてみるのは無駄ではないはずです。
それではまた!