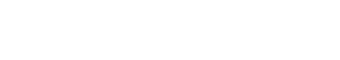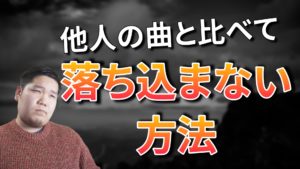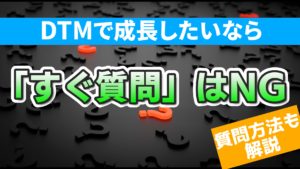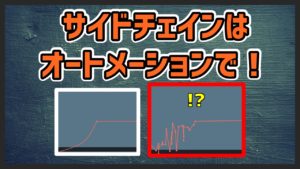どうも、作曲家のサッキー(@sakky_tokyo)です!
ミックスの解説記事や動画って、初心者向けのものばかりで、中級者以上向けのものってほとんどないんですよね。
ということで、今回の記事では中級者の方に向けて「中級者がどうやったら上級者になれるのか」ということをテーマに解説していきたいと思います。
まずは中級者と上級者の違いについて解説したあとに、中級者向けのテクニックも2つ解説するので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
【今回の動画】
今回の記事と同じ内容の動画をYouTubeで公開しています。
僕が実際に作った曲のプロジェクトファイルで解説しているので、音声付きで勉強したい方はYouTubeからご覧ください。
文字で読みたい方は、このままこの記事を読み進めてください。
ミックス初心者・中級者・上級者の違いとは

中級者が上級者になるためには、まず初心者、中級者と上級者がどう違うかを理解しておかなければいけません。
ということで、この記事では筆者なりに初心者~上級者を分類してしてみました。
どういう風に分けたかというと、結論から言ってしまえば以下の通り。
- 初心者:ミックスについてほとんど知らない人
- 中級者:ミックスについての知識はあるけど、それを適切に使えない人
- 上級者:知識があり、それを適切にテクニックとして使える人
ということはつまり、中級者と上級者ではそこまで知識的な差はないということになります。
初心者や中級者は「上級者だけが知っている魔法のテクニック」みたいな知識があるんじゃないかと思っているかもしれませんが、実際はそんなもの存在しません。
経験も知識とするなら上級者の方が知識があるかもしれませんが、作業自体は中級者でも知っていることを「精度を高く」やっているだけです。
つまり、上級者は中級者よりも聴いている音の問題点に具体的に気付くことができ、それをちゃんと修正するテクニックを知識から引き出してくる能力があるということ。
ということは中級者から上級者になるためには問題点を具体的に割り出せるだけの耳が必要なんです。
この能力は楽器演奏でいうリズム感や音感といったものとほとんど同じで、何度もミックスを繰り返すことで徐々に身についてきます。
ということで、
ミックス中級者が上級者になるためにはミックスを繰り返すしかない
という至極まっとうな結論に至ってしまいます。
とはいえ、ただ単純に量をこなすだけでは間違った努力をしてしまう可能性も結構高いんですよね。
例えるなら、サッカーが上手くなりたいのにキャッチボールをずっとやっているようなことが、ミックスの世界ではよく起こっています。
そんな状況に陥らないように、次にミックス上級者になるための前提条件について解説していきましょう。
ミックス上級者になるための前提条件

結論から言えば、以下の4つが上級者になるためには必要になってきます。
- 大量のインプット
- モニターツールを熟知する
- 1つのプラグインを使い倒す
- サウンドじゃなくて音楽を聴く
それぞれ、なぜ大切になってくるのか解説しましょう。
大量のインプット
これは自分の理想や好みを知るために重要になってきます。
ミックスはいろいろなスタイルがあり、さまざまな「正解」があります。
まずはその理想や自分の好みを知るために大量にインプットをすることが重要です。
モニターツールを熟知する
これは耳の基準を作るために重要になってきます。
モニターツールというのはモニタースピーカーやモニターヘッドホンなどの、音を聴くためのツールのこと。
これらの「モニター〇〇」というのは、フラットな音が出ると言われていますが、実際には機種や個体差などで音が全然違いますよね。
なので、1つのモニターツールを使い続けなければ自分の耳の基準がブレブレになってしまいます。
例えば普段は低音が大きく鳴るヘッドホンを使っているのに、ミックスのときに低音があまり出ないヘッドホンにしてしまったら、普段どおりの低音を得るためにベースを大きくしすぎてしまう可能性が高いです。
こんな自体に陥らないように、中級者の人は「これを使う!」と決めたら、それでいろいろな曲のインプットをして耳の基準を作ることが重要です。
ちなみに筆者はオーディオテクニカの「ATH-M50x」というヘッドホンをメインにしています。
低音から高音までしっかり鳴るので、ミックスのモニターヘッドホンにはオススメです。

1つのプラグインを使い倒す
「コンプならこのコンプ」、「EQをならこのEQ」といった具合に各ジャンルごとに1つのプラグインを使い倒すことで、各エフェクトがどういうものかという基準がわかってきます。
その上で他のコンプやEQを使えば、プラグインごとにどのようなサウンドの傾向なのかもわかりやすくなりますよね。
また、1つのプラグインを使い倒すことで、ノブやパラメーターそれぞれがどのような効果を生むのかがわかり、ミックスの自由度も上がります。
職人は使い慣れた道具を使うというイメージは皆さんも持っていると思いますが、ミックスをするときには使い慣れたプラグインがあるということも重要です。
サウンドじゃなくて音楽を聴く
これはチグハグな音楽を作らないために重要になってきます。
例えば美味しいショートケーキの上に、美味しい梅干しが乗っていたら不自然ですよね。
確かにイチゴも梅干しも小さくて赤くて酸っぱくて美味しいけど、そこはいイチゴにしてよ…ってなるんじゃないでしょうか。
それと同じように、ミックスでも「Aメロだけ聴き込んでAメロだけミックスする」「サビだけ聴き込んでサビだけミックスする」ということをしてしまうと、その部分部分はいい音かもしれませんが、合わせると不自然という事態に陥ってしまいます。
そうならないためには、部分的なサウンドだけでなく、音楽全体を意識して流れを聴いていくということが重要です。
中級者が覚えておくべきテクニック2選

次は中級者が身につけたいミックスのテクニックを2つ紹介します。
今回紹介するのは、音楽を自然に聴かせるためのテクニックです。
筆者が思うに、ミックスのテクニックには大きく分けて以下の2つの分野に分かれると感じています。
- サウンドメイキング
- 作った音を自然に聴かせるためのテクニック
中級者の方はサウンドメイキングはできるけど、それを自然に聴かせるテクニックが不足している印象があるので、今回は後者から2種類紹介します。
ボリュームのオートメーション
まず1つ目はボリュームのオートメーションです。

この画像のように音量を線で描くと、それ通りにDAWが読み込んで自動で音量を上げ下げしてくれるというテクニック。
これがなぜ重要になるかというと「聴いていて自然な音量にするため」です。
例えば、コンプを強めにかければ音量は一定に保つことができますが、それが自然に聴こえるかと言われればそうではないですよね。
それに、音楽というのは鳴っている音が常に変化するので、例えばAメロは楽器が少なく、サビだと増えるみたいなことがよくあります。
コンプでボーカルの音量を揃えたとしても、サビに入ったらバッキングが増えるので相対的に小さくなったり、逆にサビ合わせたらAメロやBメロが大きすぎたりということになってしまうのは想像できるんじゃないでしょうか。
そうならないために、トラックを分けて音量をコントロールしたり、オートメーションを書いて部分的に補正したりということが大切です。
動画では実際にオートメーションの効果をデモソングで解説していますので、チェックしてみてください。(時間指定してあるのですぐにチェックできます)
空間系のオートメーション
空間のオートメーションも自然に聴かせるために重要になってきます。
例えば、楽器が増えたときには深めに空間系をかけないと残響音が聴こえなくなりますが、途中で楽器が減ったのにそのままだと残響音が大きすぎて不自然ですよね。
なので、そういったときには空間系のセンド量(インサートならMIX量)にオートメーションを書いてあげることで丁度いいリバーブ感にしましょう。
このテクニックも動画だと音声付きで解説してあるので、ぜひご覧ください。(時間指定してあります)
おわりに
以上がミックス中級者向けの解説でした!
繰り返しになりますが、中級者が上級者になるためにはミックスを繰り返して、耳を育てなければいけません。
それなりに時間がかかりますが、一度身につけてしまえば音感やリズム感と同じくほぼ一生モノの能力になるので、ぜひチャレンジしてみてください。
また、筆者は音楽関連の講座動画をYouTubeでたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録お願いします!
筆者のツイッターはこちら!