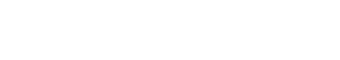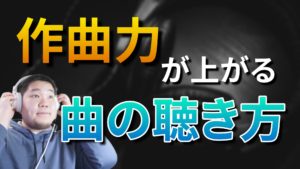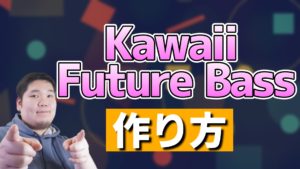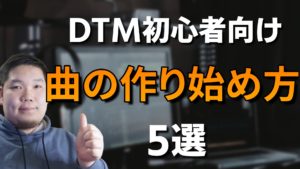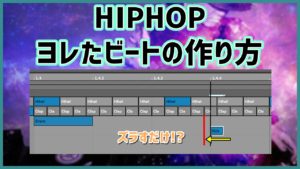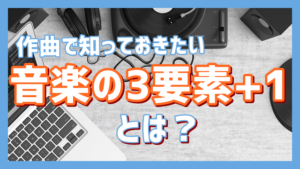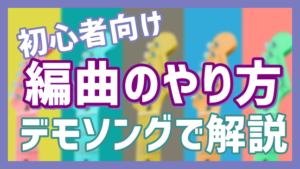テレビ番組でも、日常のありとあらゆる音がドレミに聴こえる人などがよく登場しますよね。
テーブルを叩いた音や、雨の音などまでもが音程で聴こえるというタイプの絶対音感の持ち主です。
そういった人が聴いた曲をすぐさま楽譜に起こしたりピアノで弾いたりする特技を披露しているところをテレビで観たことある人も多いでしょう。
それを観て「やっぱり音楽的な才能がある人は、絶対音感を持っているんだな」と思う人が増えていていきました。
逆に、「自分は絶対音感を持っていないから作曲も無理なんだ」と諦めてしまう人もいるんじゃないでしょうか。
今回の記事では、作曲家である筆者サッキー(@sakky_tokyo)が、そんな人に向けて、以下の疑問を解説していきます。
- 作曲に絶対音感は必要なの?
- そもそも絶対音感ってなに?
- 絶対音感と相対音感の違いとは?
それでは早速解説に移りましょう。
作曲に対する世間のイメージと現実の違い

冒頭でもお話した通り、なぜか多くの人は「作曲=絶対音感がないとまともな曲は作れない」と思っている人が一定数いるようです。
つまり、世間的には「絶対音感=音楽家に必要不可欠な才能」という認識です。
ですが、歴史を振り返ってみると歴史に名を残すレベルの偉大な作曲家でも絶対音感を持っていない人はたくさんいました。
たとえばワーグナーやハイドン、ブラームスなど、皆さんも音楽の教科書で目にしたような作曲家も絶対音感を持っていなかったとされています。
しかしながら、それでも素晴らしい楽曲を残してきたのです。
ではなぜ、絶対音感を持っていなかったのに素晴らしい曲を作ることができたのでしょうか。
結論から言えば、彼らは相対音感を持っていたからです。
相対音感と絶対音感の違い

相対音感という言葉自体は聞いたことがあるけれど、絶対音感との違いがよくわかっていないという人も多いんじゃないでしょうか。
相対音感を理解するには、そもそも絶対音感とは何なのかを理解しなくてはいけません。
絶対音感というのは、簡単に言えば「聴いた音の音程を瞬時に直感的に理解できる能力」のこと。
聴いてドレミがすぐわかるというのがポイントです。
それに対して、相対音感は「基準の音からの高低の距離を測れる能力」のこと。
相対音感の持ち主は、鳴っている音の幅を測ることに長けています。
「さっきの音がドだとするなら、今の音はミ」というように、基準からの距離によって音程や音名を答えることができる能力です。
さらに特徴として大きいのが、身に付けられる年齢です。
絶対音感を身につけるためには幼少期からの訓練が必要になると言われていますが、相対音感はどんな年齢でも身につけることができます。
日本には絶対音感信仰がある

説明したようにあくまでも絶対音感は何も頼らずに音程がわかるだけの能力。
絶対音感はその人が持つ芸術性や感受性とは全く関係ありません。
ですが、日本では何故か「絶対音感を持っている=芸術性も持ち合わせている」という勘違いがはびこっていますし、それが行き過ぎたせいで「絶対音感を持っていない自分に音楽は無理だ」と思い込んでしまう人もいます。
ですが、それはあくまで日本だけの話。
世界を見てみると、むしろプロの音楽家や作曲家で絶対音感を持っている人は少数派です。
というのも、日本のように幼少期から英才教育としてピアノを習わせる習慣や文化のある国はそこまで多くないので、絶対音感を持たないままある程度の年齢まで育ち、その後自分でプロを志して音楽を始めるパターンが多いんですよね。
そういった、あとから音楽の道を志して本気で取り組んできた人はかなりの精度の相対音感が身についています。
逆に、日本の場合は絶対音感を持っている人は多いけれど、相対音感が弱いという研究結果も存在しているんです。
研究の結果、日本の音楽大学は6割近くの学生が正確な絶対音感を持っているのに対し、中国では4分の1程度、ポーランドでは1割程度だった。
日本は世界的に見て絶対音感を持つ音楽学生が多いことがわかった。
これに対し、正確な相対音感を持つ学生の割合は、中国で4分の1程度、ポーランドでは7割を超えるのに対して、日本は1割に達しなかった。
また、学生個人の絶対音感と相対音感の正答率を見ると、日本の音楽学生は、絶対音感は優れているが、相対音感が弱いこと、ポーランド・米国では相対音感は優れているが絶対音感が弱いことが明らかになった。
もしかしたら、日本には「自分は絶対音感を持っているから大丈夫」と相対音感を鍛えることをしない人もいるのかもしれませんね。
そういった点でも日本では絶対音感信仰的なものが存在するように感じます。
作曲には絶対音感が必ずしも必要ではない

結論としては作曲をするにあたって、絶対音感は必ずしも必要ではありません。
もし今の時点で絶対音感を持っていなくても、どんな年齢からでも相対音感は身につけられるので安心して作曲に取り組みましょう。
もちろん、相対音感を身につけるためには年単位の練習が必要になります。
絶対音感がいらないからといって音感トレーニングをしなくていいというわけではありませんので、その点は注意してくださいね。
また、筆者は音楽関連の講座動画をYouTubeでたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録お願いします!
筆者のツイッターはこちら!